受験前や有名な神社に行くと、ついついお守りを買ってしまいますよね。

大切なお守りがもし壊れたらどうしよう…。
もしかしたら壊れたことによって、何かよくないことが起こってしまうかもしれない…。
大切なお守りが壊れると、どうしても不安に感じますよね。
しかし、お守りは壊れるタイミングによって、良いことの前兆を指しているのです。
大切なお守りが壊れたからと、落ち込まないでくださいね。
また、お守りにもいろんな種類がありますが、もし壊れたとしても、直すことができたら嬉しいですよね。
お守りが壊れたとき、自分の手で直してもいいのか、返納するべきなのかなどもご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
もしお守りが壊れたらどうしよう?

今持っているお守りが、壊れたらどうしようと考えたことはありませんか?
大切に扱っていても、長年持ち続けると形あるものいつかは壊れてしまいますよね。
お守りについて学べば、壊れたとしても慌てる必要はありません。
まずはお守りとは何かについて、ご紹介いたします。
お守りとは
お守りとはお守札のことを指し、持ち歩くと災いから守ってくれます。
お守り袋の中に内符(ないふ)があり、よくお守りを開けてはいけないと言われたものです。
内符とは、紙や木に経典の呪文や神名などが書かれているものを指します。
この内符が壊れたり汚れたりすると、効力も弱まります。だからお守りを開けてはいけないと言われるんですね。
お守りの本体とは、内符のことと言っても過言ではありません。
ちなみに、お守りを数える時の単位は体(たい)です。一体二体と数えます。
また、お守りは授けると言うように、神様仏様から授かるという考え方から生まれたものです。
その考え方からお守りを持つことで、さまざまな力を授かり、発揮できるかもしれませんね。
お守りの有効期限
お守りには、有効期限があるのをご存知でしょうか?
一般的には、1年間で交換することが推奨されています。
1年以内にお守りが突然壊れた時は、あなたを守ってくれたのだと思いましょう。
神社やお寺によって、期限はないと定めているところもあります。
ご自身が授かったお守りに、期限があるかどうかわからない際は問い合わせましょう。
お守りとは何かが分かったと思います。上記の通り、神様仏様から力を借りているということです。
大切に扱ったお守りが壊れることによって、縁起が悪いということはありません。
お守りが壊れたあとはしっかり供養することで、感謝の気持ちを伝えることができます。
お守りが壊れたら、返納や供養をするまで大切に保管しておきましょう。
お守りが壊れた時ってどんな意味があるの?

お守りが不自然に壊れた時は、さまざまな意味があります。
例えば紐の部分がちぎれたり、ほつれたりしてしまうなど。
勾玉など陶器であれば、割れてしまうこともあるかもしれません。
大切にしていたお守りが壊れたら、ショックですよね。
しかし安心してください。大切に扱っていたのなら不吉なことは起こりません。
お守りの種類によって、意味は異なりますので解説していきます。
願いが叶う
例えば、縁結びや金運アップのようなお守りであれば願いが叶う時です。
お守りが壊れると、願いは叶うものをご紹介いたします。
- 縁結び
- 縁切り
- 恋愛成就
- 金運上昇
- 商売繁盛
- 合格祈願
- 子授祈願
上記のお守りは、壊れた時に願いが叶うことを意味します。
ミサンガのように、ちぎれたら願いが叶うということですね。
大切なお守りが壊れた時は、突然運気も上がるかもしれません。
願いを込めて、大切にお守りを扱うことで運気が上がるかもしれません。
信じることが重要です。その願いを叶えたいと強く思いましょう。
身代わりになってくれる
例えば、健康祈願や厄除けなどのお守りは身代わりになってくれたことを指します。
お守りが壊れると、身代わりになってくれたものをご紹介いたします。
- 健康祈願
- 厄除
- 家内安全
- 交通安全
- 旅行安全
- 安産祈願
- 開運除災
上記のお守りは、あなたの身代わりになってくれたと言う意味を示します。
壊れたお守りには、感謝の気持ちを込めましょう。
カバンに入れて持ち歩いただけでも、ナイフで切れたような壊れ方をすることがあります。
そんな時は、守ってくれたと信じてみてもいいかもしれません。
どんな種類のお守りも共通して言えることは、大切に扱うことが重要だと言うことです。
壊れたお守りはどうする?

壊れたお守りは、使命を全うしたことを示します。
その際は、どうするかというと「返納すること」がおすすめです。
自宅でもお焚き上げをすることで供養できますが、複雑な手順を踏まなくてはなりません…。
簡単に供養でき、感謝の気持ちを伝えるには返納が一番ですね。
しかし、ご自身で供養したいという方もいらっしゃると思います。
ご自身で供養する際は、お清めが必要です。お清め方法もご紹介いたします。
処分するタイミングは、授かってから1年経過した時です。また、壊れた時も処分しましょう。
壊れたお守りの処分方法は、大きく分けて4種類あります。
- 神社に返納
- お寺に返納
- 郵送で返納
- 自宅で処分
返納のやり方も様々あるので、一つずつ解説していきます。
神社へ返納
神社へ返納する際の注意点を、ご紹介いたします。
お守りには、それぞれ授かった場所が記載されています。
神宮や大社と書かれていれば、神社へ返納しましょう。
一番良い方法は授かった場所へ、持っていくことです。
遠方にあり、どうしても行くことができない場合は近くの神社へ返納しても大丈夫です。
間違ってもお寺に返納はしないでください。お寺と神社は別物です。
また、必ず同じ神様のところへ返納しましょう。
神社で返納する際は、古神札納め所(こしんさつおさめじょ)へ持っていきましょう。
古神札納め所は、年中受け付けていないところもあります。
神社によっては、年始から1月下旬までしか受け付けていない場合もあります。
また返納する際、返納費用や気持ちのお賽銭が必要な場合もあります。
神社のホームページや、神社へ直接問い合わせてみましょう。
お寺へ返納
壊れたお守りをお寺へ返納する際の注意点をご紹介いたします。
お守りに寺院や寺と書かれていた場合は、お寺へ返納します。
授かった場所へ返納するのが、一番良い方法です。
しかし、遠方だったり道のりが険しかったりする場合は難しいですよね。
その場合は、近くのお寺へ返納しても大丈夫です。
注意点としては、同じ宗派であることと神社ではないことです。
仏様に感謝を伝え、お納め所へ直接持ち込みましょう。
お気持ちとして、お賽銭を納めることをオススメします。
郵送で返納
郵送で返納する時の注意点を、ご紹介いたします。
お守りを返納したいけど、授かった場所へいくことが難しい場合郵送でも返納可能です。
大きな神社やお寺の場合は、ホームページに郵送方法が記載されています。
郵送で返納する時に必要なものをご紹介いたします。
- 返納するお守り
- 返納の旨を書いた紙
- お焚き上げ料
返納の旨を書いた紙には「お守りを返納します。お守りいただきありがとうございました。(名前)」というように説明と感謝文を書きましょう。
郵送した理由を書き、感謝と名前を添えることで気持ちを込めることができます。
メモ用紙や半紙など、返納の旨を記載していれば特に規定はないそうです。
お焚き上げ料とは、その神社やお寺の定めた額を現金書留で送付しましょう。
決まった額がない場合は、お守りと同額にしておくと良いでしょう。
郵送する際は、まず送る場所に連絡を入れておくとスムーズにできます。
いきなり送ってきても、神社やお寺側がびっくりしますよね。
せっかく授かったお守りですから、壊れたあとも配慮を忘れず返納しましょう。
自宅で処分
自宅で処分する際は、必ずお清めが必要です。お清めには、白い半紙と塩が必要です。
半紙の上にお守りを置き、塩をひとつまみ持ち左回りと右回りに1回ずつかけます。
最後にもう一度、左回りに塩をかけます。これでお清めは完了です。
お清めをした後の処分方法は、2種類あります。
- 自宅で焼く方法
- 燃えるゴミに出す方法
自宅で焼く際は、必ず周囲への配慮が必要です。
家の中で焼いてしまうと火事になる恐れがあります。必ず外で行いましょう。
お守りを焼く際はお清めに使った半紙とともに、焼きます。
半紙でお守りを、包むようにしましょう。火に入れる際は感謝の気持ちを伝えましょう。
燃えるゴミに出す場合も同様です。お清めで使った半紙に包み、感謝の気持ちを伝えましょう。
願いが叶ったかどうかかかわらず、最後までありがとうという気持ちを大切にしましょう。
突然お守りが壊れた時の直す方法をご紹介!

お気に入りのお守りが壊れたら、とてもショックですよね。
しかし安心してください。外側の袋が壊れただけであれば直すことができます。
お守りの本体は内符です。外側は内符を守るためにあります。
修理可能な場合だったら、ご自宅で直しても問題ありません。
お気に入りのお守りであれば、長く使いたいですよね。
しかしご自身で修理可能かどうか、判断が難しいですよね。
修復可能かどうかの基準としては、お守りに効果があるかどうかです。わかりやすく解説していきます。
- 外側の袋のみ壊れた
- 紐がほどけた
- ゴムが切れた
- 装飾品が取れた
先ほどお守りの本体は、内符であるとお話ししました。
外側の袋だけが壊れたのであれば、直すことは可能です。
また、ご自身で新しく小袋を作って入れ直しても効果はあります。
内符を守るための袋なので、お気に入りのデザインで問題ありません。
他の壊れ方も理由は同じです。一番大切なのはお守りの核となる部分です。
キーホルダー型やブレスレット型も同じで、装飾品の鈴などが壊れても問題ありません。
ご自身で直すのは難しいと思った際、専門店にて直すことも可能です。
ご自身で修理する際は、逆に悪化させないよう気を付けましょう。
修理不可能になる条件としては、核となる部分が壊れたことです。
お役目が果たされるという意味になる壊れ方をした際は、返納しましょう。
- 内符が破けた
- 勾玉などが破れた
- 紐が切れた
内符が破けた際、お守りの効果はなくなってしまったことを示します。
外側の袋が無事だったとしても、交換することをオススメします。
身代わりになってくれたり、願い事が叶ったりした証です。
この場合は修理ができません。感謝の気持ちとともに、返納するまで大切に保管しておきましょう。
無理に修理をしたとしても、効果は発揮できません。
大切なお守りは長く使いたいですが、限界もあります。
お守りも限界以上は働くことができません。おやすみさせてあげましょう。
お役目が果たされたら授かった場所へ返してあげましょう。
えることは、大切に扱うことが重要だと言うことです。
まとめ

- お守りの有効期限は1年間
- お守りが壊れたら願いは叶う
- お守りが壊れた時は感謝の気持ちを伝える
- お守りが壊れたら返納
- 神社とお寺は別物
- 同じ神様同じ宗派に返納する
- お守りが壊れ方によって持ち続けて良い
- お守りは気持ち次第で運気が変わる
お守りは大切に扱っていても、壊れることがあります。その時は落ち込まないでください。
壊れた時はお守りの役目が終わった時なので、感謝を込めて返納しましょう。
お守りは気持ち次第で運気が上がります。叶うと信じることが大切です。
また神様から授かったものなので、乱雑な扱いをしないように気をつけましょう。

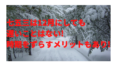

コメント